先日種まきをしたうずら豆が、発芽率ほぼ100パーセントというくらい見事に芽を出しました。
うずら豆はつる性の豆のため支柱を立てる必要があります。
本日は、うずら豆のツルが伸びだす前に支柱を立てました。
うずら豆の支柱の立て方は私の家庭菜園の師匠であるおばあちゃん先生が、手ほどきをしながら教えてくれましたので紹介します。
うずら豆の支柱の立て方
まずは芽が出て本葉が2枚~3枚になったうずら豆に軽く土寄せを行いました。
追肥は行いませんでした。
また、基本的なうずら豆の育て方には種まきは4粒ずつ播いて、成長のいい2株を残して間引くと書いてありましたが、私は2粒ずつ種まきをしてそのまま間引きは行いませんでした。
そして準備しておいた支柱ですが、こちらは物置小屋の後ろに自生している篠を相方に刈り取ってもらったモノです。
お金をかけずに支柱が準備できたことにかすかな嬉しさを感じます。
支柱の立て方です。
うずら豆の株元を囲むようにして三角形の形を作るように篠を挿していきます。
畑が固いと篠を挿すのが大変なのですが、浅いとすぐに倒れてしまうので、ここは頑張って深めに篠を挿しこんでいきます。
結構な力作業なんですよね。
三本の篠を挿したら麻紐で交差した部分を結びますが、この麻紐で結ぶ高さは目の高さがいいそうです。
師匠のおばあちゃん先生によると、「昔にそのように教えてもらったから。」ということでした。
目の高さで結ぶと、結んだ場所から上の部分が逆三角形のような形で長く上に広がっていくので、ツルもそのまま上に向かって這っていくので丁度良いそうです。
この三本の支柱を使って支柱を立てる方法は、スナップエンドウやつる制のインゲンマメ等も同じように応用できる方法なので、覚えておくと良いですよね。
支柱を立てたり、ネットを貼ったりする作業は何となく難しそな作業に思えていましたが、一つ一つ作業しながら覚えていきたいと思います。
うずら豆を栽培するのは初めてのことで、
●どんな花が咲くのか?
●どんなサヤになるのか?
●いつ頃収穫できるのか?
●どれくらい収穫できるのか?
など疑問だらけ。
この未知の世界に今からワクワクしながらその時を待ちわびている次第です。
そのためにも他の作業も頑張ろうと思える今日この頃です!
|
|
















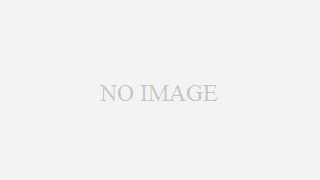

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/19795324.d7f454aa.19795325.0e162894/?me_id=1213310&item_id=19478526&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F5731%2F9784522435731.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)



コメント